令和4年11月5日(土)
本日は土曜授業。
外国語科主催の「ポプラカップ・スピーチコンテスト」が開催されており、朝から多くのお客様が来校していました。
いや~高校生の時にあれだけ話せれば・・・。
本当にうらやましい。
中学校、高校、実は小学校から英語の塾(適当に通っていただけ・・・)と学ぶ機会は頂いていたのにもかかわらず、それを活かしてこなかった自分に反省です。
もちろん思い立った今学べばよいのですが。
それでも若者には、学ぶチャンスは若いころの方がたくさんあるということを声を大にして言いたい!
さて、私は一体何をしているのか!?と思うほど午前中の時間はあっという間に過ぎ去りました・・・。
でも、午前中は本を読む時間があって幸せでした。
高橋洋一氏
安倍政権、菅政権のブレーンとして活躍した、元財務官僚、現嘉悦大学教授。
最近、YouTubeのチャンネルもそうですが、高橋洋一氏の書籍を読んでいます。
この著作は、中国の発表する経済指標には数々の矛盾が存在しているということを指摘しています。
読めば読むほど・・・。
その背景にある、中国経済の抱える構造的な問題。不動産バブル崩壊、株価の下落、そして習近平氏の独裁体制確立。
先日の党大会でも「共同富裕」(国民全体で豊かになる=富裕層のお金を貧困層へという方向性が強まる)を何度も主張していました。
世界史を学ぶと、国家を成立させる上で「思想」が不可欠であるということが分かります。
戦後の中華人民共和国は「共産主義」という思想でまとまり、毛沢東という独裁者によって強制的にまとめ上げられました。
これが1976年の毛沢東死後、鄧小平の「改革開放」政策により、政治の矛盾を「経済」で補う国家体制になったのです。
「経済」さえ上手くいっていれば、色々あるけど受け入れよう。
これは、戦間期(第一次世界大戦と第二次世界大戦の間にあった約10年間)に見られた、ナチスドイツ、アドルフ=ヒトラーの覇権獲得の構造と全く同じです。
「ヒトラーの奇跡」 失業率を25% → 5%に改善
これは積極的な財政出動(公共投資)の成果です。
アメリカ合衆国のニューディール政策しかり。
不景気の時には金融政策、財政出動、これで国民の消費意欲を高めてお金とモノが回るようにする。
さてさて、中華人民共和国は大きな岐路を迎えているのかもしれません。
「経済の繁栄」が揺らぐと、「共産党一党独裁」、「習近平独裁体制」の矛盾をどのように乗り越えていくのか・・・。
コロナ後に中国へ吹奏楽の指導に行くことを楽しみに、毎日中国語を勉強しているのですが・・・。
遠い先の話になってしまうのでしょうか・・・。
それにしても、高橋氏のご意見はなかなか過激ですが、非常にシンプルで分かりやすい。
特に、ノーベル経済学賞を受賞したバーナンキ氏に教えを受けたという点で非常に興味深いです。
マクロ経済学の理論に基づいて、現在の経済をデータで明快に説明してくれます。
色んな事が見えてきて、とても面白いです。
高校生でも十分に理解できる内容ですので、ぜひ興味があったら読んでもらいたいです。
オータムコンサートに向けて
オータムコンサートに向けての練習ですが、それはその手前にある依頼演奏の練習でもあります。
なんと来週には加須市立加須小学校創立150周年記念式典で演奏します!
150年です。
1872年でしょうか?
1868年が明治元年。
その4年後にはこの加須の地に学校が開かれたというのですから驚きです。
ちなみに1871~ 岩倉具視使節団が欧米に旅をしているころです。
いや~歴史です。
ここで演奏する作品が・・・。
まだまだ明日が見えません。
「マードックからの最後の手紙」2021年版。
何としても仕上げましょう。
500名ほどの小学生、関係者の皆様の前で、心を込めて演奏しましょう。
練習はあと平日だけ・・・。
合奏はいつできるのかな。
いや~秋のイベントシーズン。このヒリヒリする感じが懐かしいです。
部員の皆さん!!
いますぐに「火事場の○○力」出してくださ~い!!
いつも以上にドキドキしています。
SEJWB 東部支部吹奏楽団
第2回の練習となりました。
前回は修学旅行中で2年生が不在だったのですが、今回は2年生も参加して充実した練習になりました。

まだまだ固い雰囲気のある人もいますが、少しずつ慣れてきていると感じました。
基礎合奏では、3D(教本)を使って「音階」を学んだり、『吹奏楽のソルフェージュ』(楽典、ソルフェージュなど音楽の専門的な知識をまとめた教本)を使って音価、拍子の拍節感、フレーズ、休符などを学びました。
どれも、団員にとっては初めての内容だったようです。
また、「セレブレーション」の合奏では「アナリーゼ(楽曲分析)」をしました。
全員でスコアを見て、楽曲の構造を理解して演奏することの大切さを学びました。
知っていると知らないでは雲泥の差です。
何より、知らないで演奏していても楽しくありません。
理解する喜びも音楽の素晴らしさの一つです。
ぜひ、これをきっかけに「音楽の沼」にはまってもらいたいです。
2曲目の「赤鼻のトナカイ」で大苦戦・・・。
スィングをしっかりと演奏したことが無い団員が多いようでした。
食べたことの無いものの味は分かりません。
様式(スタイル)を学ぶことも大切だな~と痛感しました。
この楽団では「発表」の喜びも重要なテーマです。
12月24日のクリスマス・コンサートは思い切り盛り上げて、団員の皆さんが
「楽しい~!!」
と思える時間にします。
第3回も楽しみです!

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1ef9c85e.ea659a28.1ef9c85f.0d0ef915/?me_id=1278256&item_id=15531153&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frakutenkobo-ebooks%2Fcabinet%2F5837%2F2000004235837.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1ef9c85e.ea659a28.1ef9c85f.0d0ef915/?me_id=1278256&item_id=11647013&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frakutenkobo-ebooks%2Fcabinet%2F5638%2F2000000215638.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

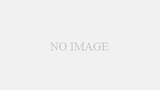
コメント